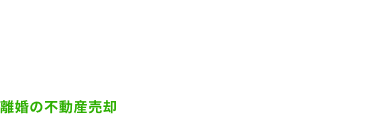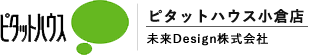宇治市で地震に備える住宅改修。空き家の活用にもつながる耐震対策とは? | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
宇治市で地震に備える住宅改修。空き家の活用にもつながる耐震対策とは?

お世話になっています。未来Designです。近年、防災への意識が高まり、持ち出し用リュックの準備や備蓄品の買い置きなど、日常の中で「備え」を進める方が増えています。
一方で、「自宅の耐震性が気になるけれど、費用面が心配で改修までは踏み切れない」という声も少なくありません。
本記事では、宇治市が実施している「耐震改修に関する補助金・助成制度」について、概要や申請の流れをわかりやすく解説します。
1.地震に関する住まいの不安

日本では地震への備えが日常の大切な習慣となっています。
宇治市にお住まいの方の中にも、地震のニュースをきっかけに「わが家の安全を見直してみよう」と考える方が増えているのではないでしょうか。
ここでは、住まいに関してよく寄せられるお悩みや気になる点を、いくつかのカテゴリに分けて整理してみました。
1-1 構造・老朽化に関する不安
●木造住宅の場合の耐震性
木造住宅にお住まいの方は、強い地震が来たときに家全体がどの程度耐えられるのか、気になることもあるでしょう。特に長く住んでいる家ほど、構造が丈夫かどうかを知ることは大切です。
●築年数の影響
築年数が古い住宅では、現在の耐震基準に沿った設計になっているかどうか分からず、改修の必要性を検討する材料に困ることがあります。どのくらいの地震に耐えられるかを確認しておくことが安心につながります。
●柱や土台の劣化
長年の生活や湿気、シロアリ被害などで、柱や土台が少しずつ劣化している場合があります。目に見えない部分の劣化も、家全体の安全性に影響するため、定期的なチェックが推奨されます。
●屋根や上部の重さ
瓦屋根など重い屋根材の場合、建物の上部にかかる負荷が大きくなることがあります。屋根の軽量化や補強によって、揺れに対する建物の安定性を高めることができます。
1-2 知識や費用に関する不安
●耐震リフォームの種類や費用
どのような耐震リフォームがあるのか、またそれぞれどのくらい費用がかかるのか分からず、情報を集める段階で迷う方も多いです。専門家に相談することで、効率よく必要な補強を選ぶことができます。
●耐震基準やリフォームの進め方
旧耐震基準と新耐震基準では求められる強度が異なるため、基準の違いやリフォームの手順が分からず不安になることがあります。書類や施工記録を確認し、必要に応じて専門家の意見を聞くと安心です。
●地震保険や補助金制度の活用
地震保険や市の補助金制度は内容が複雑に感じられることもありますが、正しく理解すれば、経済的な負担を抑えながら改修や備えを進められます。情報を整理し、制度を活用することが重要です。
1-3 生活・安全面の不安
●家具の転倒や室内の安全
実際の地震で被害を受けやすいのは、家具の転倒やガラスの飛散です。日常の工夫として、家具の固定やガラスへの飛散防止フィルムの設置、避難時の動線を考えた配置などで、安全性を高めることができます。
●耐震シェルターの設置
万が一のときのために耐震シェルターを設けたいと考える方もいます。家族を守るための有効な方法ですが、費用面で迷う方も多いのが現状です。市の補助制度を活用することで、負担を抑えながら設置できる場合があります。
1-4 空き家に関する不安
●相続した空き家の安全性
使っていない空き家がある場合、地震時の倒壊や老朽化が気になることもあります。耐震診断を受け、必要に応じて改修や整理を行うことで、資産として活用しながら安心を確保できます。
●活用方法が分からない場合
古い家をどう扱えばよいか迷う方も少なくありません。放置しておくよりも、リフォームや解体、土地活用などの選択肢を知ることで、安心して次のステップに進むことができます。
このように、住まいの安全に関する検討は「建物の強さ」だけでなく、情報や費用、生活上の工夫や空き家の管理まで、多方面にわたります。次の章では、こうした不安を少しずつ解消するための耐震対策やリフォームの具体的な方法をご紹介していきます。
2.住まいの地震に対する不安を解消する方法

不安の内容ごとに、具体的な解消方法を整理してみましょう。
2-1 構造・老朽化に関する不安への対策
●家の強さを知るために「耐震診断」を受ける
「うちの家、地震に耐えられるのかな…」と感じたら、まずは耐震診断を受けることから始めましょう。
診断を受けることで、自宅がどの程度の揺れに耐えられるのか、補強が必要な箇所がどこなのかを把握できます。 宇治市では、「木造住宅耐震診断士派遣事業」として、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、耐震診断士の派遣や診断費用の一部を助成しています。現状を知ることで、どこを優先的に直すべきかが明確になり、無駄な費用をかけずに効率よく改修を進めることができます。
●築年数の古さが気になる場合は「耐震補強リフォーム」
1981年(昭和56年)以前に建てられた住宅は、現在の耐震基準に比べて耐震性が低い可能性があります。しかし、耐震補強リフォームを行うことで、安全性を大幅に高めることができます。
たとえば、「耐力壁の追加」「接合金具の補強」「屋根の軽量化」
といったリフォームを組み合わせることで、家全体の耐震性が改善します。
宇治市の補助金制度を活用すれば、自己負担を抑えて工事を行うことも可能です。
●柱や土台の劣化には定期点検を
木造住宅では、シロアリ被害や湿気による腐食が耐震性低下の原因になることもあります。 普段見えない部分ほど、劣化が進みやすいものです。5〜10年ごとに専門業者による定期点検を行い、柱や土台の状態をチェックしておくことが、長く安心して暮らすためのポイントです。
2-2 知識や費用に関する不安への対策
●家の基準を知り、地元業者に相談する
耐震性は、家が「いつ建てられたか」で大きく異なります。
旧耐震基準(1981年5月まで)は震度5程度、 新耐震基準(1981年6月以降)は震度6〜7に耐える設計になっています。
どちらで建てられているか分からない場合は、 役所や不動産会社で建築確認日をチェックしてもらいましょう。
また、リフォームを検討する際は、 宇治市の補助金制度を知る地元の不動産会社へ相談するのがおすすめです。 たとえば、未来デザインでも、耐震改修のご相談を随時受け付けています。 小さな疑問でも気軽にお問い合わせください。
●保険・補助金を上手に活用
地震への備えには、経済的な対策も欠かせません。
火災保険に付帯できる地震保険を利用すれば、被害に応じた補償を受けられます。
さらに宇治市では、昭和56年以前の住宅を対象に耐震診断費用の補助制度を実施中です。
補助金や制度を賢く活用して、いざという時に備えましょう。
2-3 生活・安全面の不安への対策
●家具の転倒やガラスの飛散に備える
地震によるケガの多くは、建物の倒壊よりも家具の転倒やガラスの飛散によるものです。
日常の少しの工夫で、被害を大きく減らすことができます。
・家具をL字金具や突っ張り棒で固定する
・ガラスには飛散防止フィルムを貼る
・枕元にスリッパや靴を置いて避難時のケガを防ぐ
・非常用持ち出し袋を玄関や寝室に常備しておく
こうした対策を日頃から取り入れることで、安心感がぐっと高まります。
●「耐震シェルター」で命を守る最後の空間を
老朽化した住宅では、家全体を補強するよりも耐震シェルターを設置する方が現実的な場合もあります。シェルターは「家の中に命を守る空間をつくる」という発想で、万が一の倒壊時にも生存空間を確保できます。現在、宇治市では耐震シェルター設置に対する補助金制度も実施中です。費用面がネックだった方も、条件を確認して一度検討してみましょう。
2-4 空き家に関する不安への対策
●空き家の倒壊が心配な場合は、診断・改修・解体の検討を
相続したまま放置している空き家がある場合は、まず耐震診断を受けてみましょう。改修を行えば、住まいや賃貸物件としての資産価値を再生することも可能です。一方で、危険度が高い老朽空き家の場合は、宇治市の老朽空き家等解体補助金制度を利用して、解体・土地活用を進めるのも一つの方法です。「倒壊リスクをなくしながら資産として活かす」ことが、これからの空き家対策の鍵になります。
3.宇治市の木造住宅耐震改修等事業費補助金について

宇治市では、過去の地震で木造住宅が被害を受けたことを踏まえ、令和7年現在、木造住宅の耐震改修や簡易耐震改修、屋根の軽量化、壁・接合部・基礎の補修などの費用に対して、補助金制度を充実させています。
対象期間:2025年4月1日~2025年1月16日
補助額の目安:上限137.5万円 → 145万円、補助率 約92% → 約97%
補助金を受けるためには、いくつかの条件があります。
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(簡易改修の場合や一部損壊の場合は条件緩和あり)
・宇治市の指定区域内に建設されていること
・住宅以外の用途がある場合、住宅部分が床面積の2分の1以上であること
・国や京都府など他の公共機関の補助金を受けていないこと
・市税の滞納がないこと
さらに、改修内容に応じて補助区分と上限額が決まっています。
・耐震改修A:建築士による診断で評点1.0未満の住宅を、改修後1.0以上に改善(上限145万円)
・耐震補修B:同じく診断で評点1.0未満の住宅を、改修後0.7以上に改善(上限100万円)
・簡易耐震改修:耐震性向上が見込める簡易工事(上限40万円)
4. 耐震シェルター設置補助
耐震シェルターは、大地震時に家屋が倒壊しても、シェルター内に避難することで命を守る「最終防衛ライン」となる設備です。特に、昭和56年以前に建てられ、耐震改修が難しい住宅に対して、宇治市では設置費用の一部を助成しています。
補助内容:設置費用の4分の3を補助(上限30万円)
耐震シェルターを取り入れることで、家族の安全を守る時間を確保でき、今後の住宅に備える有効な選択肢となります。
5.空き家関連の補助金について

5-1 空き家の耐震改修も補助対象に
耐震改修の区分において、空き家(概ね1年以上使用されていない状態の住宅)は、補助率がさらに高くなります。
・耐震改修A:改修に要する経費の100%(上限170万円) ・耐震改修B:改修に要する経費の100%(上限125万円)
このように、空き家の場合は自己負担をほとんどかけずに改修を行える可能性があります。 「しばらく使っていない家をどうしようかな」と思っている方も、この機会に耐震改修へ取り組んでみるのも良いでしょう。
5-2 耐震改修は空き家の再活用に
耐震補強を行うことで、空き家の使い道が広がります。
・売却前に耐震補強をして資産価値を上げる
・改修して賃貸住宅や店舗として活用する
・家族の住まいとして再利用する
住宅の安全性が確保されることで、売るにも貸すにもメリットが増し、空き家の再活用が現実的になります。耐震改修は“支出”ではなく、“資産価値を守るための投資”と言えるでしょう。
5-3 令和7年の空き家関連助成制度
宇治市では、耐震補助以外にも多様な空き家関連の助成金制度が用意されています。
・新婚世帯住宅確保おうえん事業補助金
・子育て世帯住宅確保おうえん事業補助金
・宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)
・老朽空き家等解体補助金
・まちなみ景観保全につながる空き家活用アドバイザリー業務補助金
・地域コミュニティスペース創生事業
・空き家と地域の共生応援制度
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修補助金
これらの制度を活用することで、「空き家を売りたい」「貸したい」「買いたい」「借りたい」「解体したい」など、それぞれの状況に合わせたサポートを受けることができます。諸条件や申請期限、補助金の上限額などは制度によって異なります。まずは地元の不動産会社に相談し、市役所で確認のうえ申請を行ってから、工事や利活用を進めていきましょう。
まとめ

耐震改修は、地震への備えであると同時に、空き家の再生や地域全体の安全にもつながる大切な取り組みです。老朽化した住宅を放置すると倒壊や延焼などのリスクが高まりますが、耐震診断や補強工事を行うことで「安心して暮らせる住まい」へと再生することができます。
宇治市では、診断・改修の両方に対して補助制度が整っており、上手に活用すれば費用負担を抑えて確実に耐震性を高めることが可能です。
また、空き家も耐震改修を施すことで、再利用や賃貸・売却など新たな活用がしやすくなり、地域の防災力向上にも貢献します。放置すれば「リスク」になる建物も、少しの手入れと補強で「価値ある資産」へと生まれ変わります。
まずは、地元の不動産会社や専門業者の無料耐震相談を利用し、今の住まいの状態を確認することから始めてみましょう。
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
理想の物件がきっと見つかる