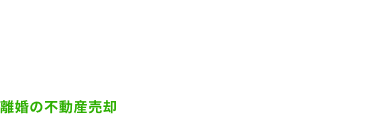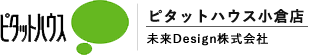スマホで確定申告ができる?確定申告の手順や必要書類について解説! | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
スマホで確定申告ができる?確定申告の手順や必要書類について解説!

「確定申告が面倒!」
「もっと簡単に確定申告を終わらせる方法はないの?」
新しい年を迎えると、確定申告に向けて憂鬱になる方もいるのではないでしょうか。
必ず申告しなければいけないけど、なるべく手間をかけずに終わらせたいですよね。
そんな方におすすめしたいのがスマホで確定申告です。
・確定申告は面倒臭い
・人混みには行きたくない
・忙しくて確定申告会場に行けない
そう考えている方にスマホで確定申告は最適です。
本記事ではスマホで確定申告の方法や用意するものを紹介します。
もっと手軽に確定申告ができないか、お悩みの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
【スマホでの確定申告が向いている人】

税務署や申告会場で申告した方が安心なのでは?とスマホでの申告に不安を感じる方もいるかもしれません。では、どのような人がスマホでの確定申告に向いているのでしょうか。
・個人事業主の方
個人事業主として仕事を受注している方の中には、会計や確定申告を税理士にお願いしている方もいますが、会計ソフトなどを使用して自分で全てを管理している方も多いですよね。
普段から自分で会計を管理しているいるという個人事業主の方なら、スマホを使って簡単に申告できる「スマホ確定申告」が向いているでしょう。
・忙しくて隙間時間に申告したい方
スマホでの確定申告は移動中の電車やタクシー、仕事の休憩中などでも行うことができるため、忙しくて申告会場に行く時間が取れない方に向いています。
時間や場所を考えずにできることがスマホ確定申告の最大の特徴です。
・面倒なことが苦手な方
領収書やレシートを一枚ずつ確認しながら申告書に書き込むのが面倒、という方もいますよね。そんな方にもスマホ確定申告がおすすめです。
スマホ確定申告では、面倒な税金の計算をアプリで行うことができます。面倒な作業が苦手な方は一度試してみてはいかがでしょうか。
【スマホで確定申告する方法】

ここではスマホで確定申告をする方法を①会社員の場合②個人事業主の2つのケースに分けてご紹介します。
①会社員の場合
会社員の場合、会社が年末調整をしてくれるため、確定申告とは無関係というイメージがあるかもしれません。しかし確定申告ができるケースがあります。
・医療費控除の申告
自身や扶養に入っている子供、家族が通院・入院した際の医療費を控除することができます。確定申告をすることで税金が還付される場合もあり、スマホで申告が可能です。
・副業の申告
本業以外で副業をしている会社員もスマホで申告することができます。
| 対象所得 | ・給与所得 ・雑所得 ・一時所得 ・特定口座年間取引報告書(令和3年度分より) ・上場株式等の譲渡損失額(前年繰り越し分。令和3年分より) |
| 対象控除 | ・すべての所得控除 ・政党等寄附金特別控除 ・災害減免額 ・外国税額控除 ・予定納税額 ・本年分で差し引く繰越損失額 |
ただし、上記以外の不動産所得や、事業レベルで収入が大きい事業所得の場合はスマホ申告ができないので覚えておきましょう。
②個人事業主の場合
個人事業主の場合、スマホから国税庁の「確定申告等作成コーナー」で事業所得の申告をすることはできません。なぜならスマホからの申告が未対応になっているためです。
一方で、クラウド会計ソフトを利用している個人事業主であればスマホからの確定申告が可能です。
【申告時に用意するもの】

スマホの確定申告で準備するものは以下の通りです。
・スマホ
Android端末やiPhoneを用意します。iPadでも可能です。
・源泉徴収票
給与額などを確認しながら入力するため、会社から発行される源泉徴収票を手元に準備してください。
・マイナンバーカード
マイナンバー方式を利用する場合に必要になります。
申請書にマイナンバーの記載が必要になるため準備しておきましょう。
【スマホで確定申告する流れ】

国税庁が提供している確定申告サービス「e-Tax」を利用するときの手順を紹介します。
1.確定申告書等作成コーナーから開始
まず、国税庁の確定申告書等作成コーナーから作成開始をクリックします。
2.質問や提出方法を入力
次に質問に「はい」「いいえ」で回答していきます。提出方法を「マイナンバー方式」「ID・パスワード方式」「書面」から選択します。
3.マイナンバーカードを読み取る
マイナンバー方式を選択する場合は、マイナンバーカードの読み込みを行います。
ID・パスワード方式の場合はID・パスワード方式の届出完了通知にある利用者識別番号を入力後、e-Taxへのログインを行います。
4.源泉徴収を参考に入力
手元に用意した源泉徴収票を見ながら、支払金額などの数字を入力します。
令和3年分の確定申告より、スマホで撮影した源泉徴収票が自動で読み込まれるようになりました。
5.住民票に関する情報などの入力
住民票を参考に16歳未満の扶養家族の情報や申告者の情報を入力します。
6.データ送信
最後に入力した情報を送信して完了です。「受付結果を確認する」でデータが正常に受け付けされたかを確認しましょう。
【スマホで医療費控除の確定申告をする】

先述した通り、スマホで確定申告を行う場合も、医療費控除は可能です。
スマホで医療費控除を受ける場合、一般的には以下の書類が必要となります。
・医療費の領収書
・医療費通知(健康保険組合などから医療費通知を受け取っている場合)
・医療費通知データ(医療費通知データを読み込む方法の場合)
※このほかにも、医療費の内容によってはオムツ使用証明書などの証明書が必要になるケースがあります。
スマホで医療費控除をする場合の方法は「確定申告ソフト(アプリ)」か「確定申告書等作成コーナー」の主に2通りになります。
確定申告書等作成コーナーでスマホから医療費控除をする際の方法は、「医療費の領収書から入力する方法」「医療費通知データを読み込む方法」「マイナポータル連携で自動入力する方法」の3つがあります。医療費控除に必要な書類と合わせて、それぞれの方法をみていきましょう。
1.確定申告ソフト(アプリ)で行う方法
医療費控除の確定申告に対応したアプリをダウンロードして行います。
例えばマネーフォワード クラウド確定申告アプリでは、医療費控除やセルフメディケーション税制の確定申告を簡単に行うことができます。
2-①医療費の領収書から入力する方法
確定申告書等作成コーナーで作成する方法のうち、医療費の領収書をみながら医療費の明細をスマホで入力していく方法です。
スマホの確定申告画面を進めていき、提出方法や収入の項目などを入力していきます。
①医療費控除→②適用する医療費控除を適用→③医療費通知、領収書、医療費集計フォームから入力する→④行いたい方法を選択し必要事項を入力、これで医療費控除の申請が可能です。
出てくる画面に沿って自身が行いたいものを選択していくだけで、医療費控除の確定申告ができます。
2-②医療費控除の金額を自動計算する方法
確定申告書等作成コーナーで作成する方法のうち、健康保険組合から受け取った医療費通知データを読み込んで、医療費控除の金額を自動計算する方法です。
スマホの確定申告画面の申告準備→xmlデータの読み込み→ファイルを選択で該当データを読み込みます。
データ読み込み後、控除入力画面の医療費控除で医療費控除の金額が自動計算されています。医療費通知データに記載されているもの以外に医療費がある場合には修正も可能です。
2-③マイナポータル連携で自動入力する方法
マイナポータル連携とは、マイナポータルを経由して控除証明などに必要なデータを一括で取得する方法です。 令和4年から、医療費通知データもマイナポータル連携の対象となりました。
【スマホで確定申告をした場合の納税方法】

スマホでの確定申告が完了したら、追加納税が必要かどうかを確認します。様々な納税方法を選択できるため、自分にあった方法を選びましょう。
1.銀行振替
納税者であるあなたの金融機関口座から、引き落としの手続きを行う納税方法です。最初に手続きさえしておけば以降は自動的に引き落とされます。
自分から支払いにいくのが面倒...という方におすすめの方法です。確実に引き落とされるように残高を確認しておく必要があります。
2.現金納付
金融機関や税務署に出向いての現金納付も可能です。納付書が必要になるため、金融機関や税務署にあるものを用意しましょう。
3.コンビニ支払い
家や職場の近くにコンビニがある場合はコンビニ納付も便利です。コンビニ納付用のQRコードを作成して持っていきましょう。
4.クレジットカード
すぐに納税を済ませたい方はクレジットカード決済がおすすめです。税金の種類や納税金額、クレジットカード情報などを入力すれば納税が完了します。
5.e-TAXで支払う
e-TAXは国税電子申告・納税システムのことを指します。消費税や所得税などの申告をインターネットを使って行うことができます。
さらに税金の納付もインターネットバンキングなどを利用して行うことが可能です。
まとめ

スマホでの確定申告は忙しくて時間がないという方や、少しでも手間を省きたいという方におすすめの方法です。
確定申告の時期は毎年やってくるので、スマホだけでなく、税理士などのプロに頼む方法など自身の生活にあった方法を選択して、少しでも負担を減らしながら確定申告を進められるといいですね。
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
理想の物件がきっと見つかる