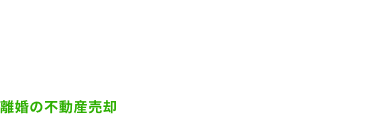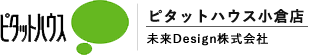シングルマザーにおすすめの保険6選・保険選びのポイント3点についても解説! | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
シングルマザーにおすすめの保険6選・保険選びのポイント3点についても解説!

シングルマザーは、1人で仕事、育児、家事を担うため、体力的に無理が生じてしまったり、経済的に苦しい状況になってしまう可能性があります。そのため、病気やケガをして働けなくなった場合や、子どもの養育費が多くかかるタイミングなどを見据えて、保険の加入を検討する方もいるのではないでしょうか。
今回は、シングルマザーの方におすすめの保険や、保険を選ぶ際のポイントについて解説します。
1.シングルマザーが保険に入っておくと安心な3つの理由
シングルマザーにとって、保険に加入しておくとさまざまな面で安心できるでしょう。ここでは、シングルマザーに保険が必要な理由を3点お伝えします。
①子どもの養育費への備え
子ども1人あたりにかかる、幼稚園から大学卒業までの養育費は、2,000万円以上といわれます。子どもの養育費は、特に大学や専門学校など高校卒業以降に大きなお金が必要となります。いざという時に必要なお金が使えるひとつの方法として、保険への加入が挙げられます。
同時に、万が一、自分が働けなくなった場合に、子どもの養育費をどのように賄うのかも考えておく必要があります。
このような状況もカバーできる保障のついた、保険を選ぶとよいでしょう。
②病気やケガへの備え
1人で家事・育児を行う母親が病気やケガを負ってしまうと、仕事を休むことによる収入減や治療費がかかることが予測できます。
そのような場合に備えて保険に加入していれば、収入が減ったり絶たれたりした際にも一時金を受け取ることが可能です。
病気のなかでも治療が長期に及ぶ可能性のある、がんに特化した保険もありますので、自分に合ったものを選びましょう。
③本人が死亡した場合の備え
シングルマザーとして1人で子どもを育てていると、一番の不安は自分が死亡した場合に子どもが残されてしまうことではないでしょうか。
仮に親族などが子どもを育ててくれることになったとしても、子どもが自立するまでにはさまざまなことにお金がかかります。親が亡くなった場合には、公的な遺族年金も支給されますが、それだけでは生活費や学費が不足してしまう場合もあります。
自身の万が一に備え、後で詳しく解説する、死亡保険も検討しておくとよいでしょう。
2.シングルマザーにおすすめの保険6選

ここでは、シングルマザーにおすすめの6つの保険についてご紹介します。
①学資保険
前項の最初に養育費のことに触れたので、まず学資保険についてご紹介します。
学資保険とは、契約時に定めたタイミングになると、保険金やお祝い金を受け取ることのできる貯蓄額の保険です。 契約時に定めるタイミングは、
・大学入学時
・大学入学以降、4~5年間
・小中学校、高校などの入学時
といった、子どもの学費が多くかかる時期に設定します。
学費を銀行口座などに貯めておくと、ついつい使ってしまうという方の場合、保険金を受け取る際に解約が必要な学資保険はおすすめです。
②医療保険
医療保険とは、病気やケガを負った場合の入院や手術、通院などの費用を保障する保険です。
健康保険など公的な医療保険もありますので、そちらの内容も確認しておく必要がありますが、受給するためには、一定の条件を満たさなければなりません。
民間の医療保険に加入しておくことで、入院や手術をした場合に一時給付金を受け取ることができますし、内容も多岐にわたります。病気やケガに手厚く備えておきたいという方は、検討してみてもよいでしょう。
③がん保険
がん保険とは、文字通り、がんになった場合に保障が受けられる保険です。
給付金が受けられるタイミングは、(1)がんと診断されたとき(2)がんで入院した場合(3)がんで通院した場合(4)がん専門の治療をした場合などがあり、保険によって異なります。
現在では、乳がんや子宮頸がんに対して手厚い保障のある、女性向けの保険もあります。乳がんや子宮頸がんは若い女性も患う可能性のある病気ですので、早い段階からしっかりと備えておきましょう。ただし、これらの女性に特化した保険は、保険料が高くなる傾向にあるため、収入とのバランスをしっかりと考慮することが大事です。
がんの専門治療には多額の費用がかかります。これは、公的な「高額医療制度」を利用することも可能ですが、がん保険に加入しておくとさらに安心でしょう。
④収入保障保険
収入保障保険とは、保険の対象者が死亡または高度障害など万が一のことがあった場合、その家族に一定額の保険金が毎月支払われる保険です。親に、万が一のことが起きた場合に保険料を学費や生活費にあてられるため、特に小さい子どもがいる方におすすめの保険です。
年金形式で受け取れるため、生活費などを補うことができます。収入保障保険は、保険の満了期間が近づくにつれ、毎月支払われる保険金が減額します。そのため、毎月の掛け金も定期保険に比べると割安になる傾向があります。 保険の満了期間は、受け取る家族が子どもの場合、独立をすると自分で収入を得られるようになるため、子どもが独立できる年齢を目処に考えるとよいでしょう。
⑤就業不能保険
就業不能保険とは、病気やケガで入院し働けなくなった場合に、保険期間の満了時、または働けるようになるまで、毎月一定額の保険金が支払われる保険です。就業できない期間の収入減に備えることができます。
病気やケガで入院し働けなくなった場合には、健康保険組合から「傷病手当金」が支給されますが、支給金額は、「働けなくなったときから過去12ヶ月の平均収入の三分の二まで」です。また、支給期間は、最大1年6ヶ月となっています。一方、就業不能保険は高齢になるまで保障が受けられるプランもありますので、長期間の休職や収入減に備えて加入を検討してみてもよいでしょう。
ただし、就業不能保険には保険金が支払われない免責期間や保険金の額が減額される期間もあります。加入を検討する際は、これらの条件をしっかりと確認するようにしましょう。
⑥死亡保険
死亡保険は、被保険者(保険の対象者)が死亡した場合に保険金が支払われる保険です。
死亡保険は、保険期間が限定的で保険金を一括で受け取れる「定期保険」と、保険期間が一生涯となっている「終身保険」の大きく2種類に分けられます。
通常、親が亡くなった場合には、残された子どもに対して「遺族年金」が支給されます。しかし、遺族年金や貯金だけで生活していくことが難しい場合もあるでしょう。そのような場合の生活費や教育費を死亡保険で補えるように、加入を検討してみてもよいかもしれません。
3.保険を選ぶ際の3つのポイント
保険を選ぶ際、家計とのバランスなど、自分でもさまざまな試算をしておくことが重要です。 ここでは、保険の加入を検討する際のポイントを3つご紹介します。
①毎月の支出をできるだけ抑えられる保険に加入する
しっかりと備えをしておきたいからといって、多くの保険に加入してしまうと月々の保険料が高額になり、家計を圧迫してしまう可能性があります。
そのような状況にならないよう、重視する補償内容を絞ってみましょう。その際、生活費にも子どもの学費にも使えるような、用途の多い保険も検討するとよいかもしれません。
また、保険料の払込期間が長期になればなるほど、月々の保険料の金額は下がります。ですから、加入するのであればできる限り早めに手続きを行うとよいでしょう。
しかし、払込期間が長期になることで、一定期間で満期になる保険に比べると保険料の払込総額は増えることになります。
保障内容、月々の保険料、満期になるまでの保険料総額など、自分の収入に合ったバランスを考えるようにしましょう。
②教育費を試算してみる
子どもの人数や現在の年齢、どのような教育を受けさせたいのかということによって、子どもにかかる養育費は異なります。
小学校から大学・専門学校まで、公立・私立に通った場合にそれぞれいくらくらいの費用がかかるかはインターネットなどで調べられますので、それらも参考にして養育費を試算し、養育費を保険で準備するかどうか、検討してみましょう。
③万が一の医療費・入院費を試算してみる
万が一、自分が病気やケガで入院する場合も想像して、かかる費用を試算してみましょう。手術や入院となった場合には、まとまったお金が必要です。また、入院する場合は、相部屋か個室かによってもベッド代が異なります。
また、病気やケガによる入院などで働けなくなった場合には、収入が大幅に減少する可能性があります。会社で健康保険に入っていれば、就業不能保険で解説した「傷病手当金」により、月収のおよそ2/3を最長1年6ヵ月間受け取ることができます。しかし、パートやアルバイト、自営業、専業主婦の方などで国民健康保険に加入している場合には、そのような制度はないため、自分で備えておく必要があります。
さらに、入院中の子どもの面倒は誰にみてもらうのかということも考えておきましょう。その間の子どもの生活費や預け先や世話のための費用も試算し、加入する保険を検討しましょう。
シングルマザーの支援、どんな種類がある?助成金や手当をご紹介!
シングルマザーの助成金・手当、不正受給扱いになるのはどんなとき?
婚姻歴や性別に関わらず、ひとり親を対象にした所得控除「ひとり親控除」についてはこちら
まとめ

仕事・家事・育児を1人で担うシングルマザーは、体力的にも経済的にも大きな負担を背負うことになります。だからこそ、万が一に備えて保険に入っておくと、働けない間の収入をカバーできたり、安心して子どもに教育を受けさせたりすることができるでしょう。今回、ご紹介したように保険にはいろいろな種類があり、パターンによって料金もさまざまです。自分一人で考えるのが不安な場合は、保険のプロに相談してみると、自分に合った保険を提示してもらえたり、アドバイスをもらえるでしょう。
家計とのバランスを見ながら、無理のない範囲で、自分に合った保険を選べるといいですね。
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
理想の物件がきっと見つかる