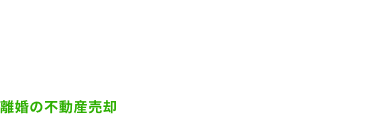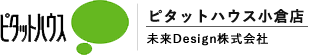建築基準法とは?2025年4月の改正点とその影響をわかりやすく解説 | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
建築基準法とは?2025年4月の改正点とその影響をわかりやすく解説

家を建てるとき、リフォームをするとき、また不動産を購入・売却するとき、必ず関わってくるのが「建築基準法」です。 この法律は、私たちの暮らしの安全を守る重要な役割を果たしていますが、2025年4月に一部が改正され、より柔軟で持続可能な建築・都市計画を目指す内容が盛り込まれました。 この記事では、建築基準法の基本的な考え方と、2025年改正の注目ポイントをわかりやすく解説します。
1建築基準法とは?

建築基準法は1950年に制定され、建物の安全性や快適な都市環境を守るための基本ルールとして、時代の変化に合わせて改正が重ねられてきました。地震・火災への備えや省エネ、災害対策なども反映されています。
①安全性の確保
地震や火災に備え、耐震構造・耐火性能・避難経路の確保など、建物の構造や設備に関する基準が定められています。
②健康的な生活環境の維持
快適で衛生的な住環境を確保するため、採光・換気・トイレや排水設備などについてのルールがあります。
③都市景観と秩序の維持
無秩序な開発を防ぎ、用途地域・建物の高さ・容積率や建ぺい率の制限を設け、調和の取れた街並みを守ります。 これらのルールに基づき、建物を建てる際には建築確認申請などの手続きが必要になります。
2.建築基準法2025年4月の主な改正点とは?

2025年4月の改正では、国が2050年に向けて進めているカーボンニュートラル達成に向けて、省エネの強化、木造建築の推進、木造住宅倒壊の防止といった観点から改正が行われました。 以下、主な改正点を6つご紹介します。
①「4号特例」の縮小
「4号特例」とは、小規模な木造住宅などについて、建築確認の際に構造や防火に関する審査が一部省略される特例制度です。正式には、建築基準法第6条第1項第4号に定められていることから「4号建築物」または「4号特例」と呼ばれています。
■改正のポイント このような建物は、従来は「小規模・一般的な住宅」として扱われ、建築士による設計であれば、行政による構造や防火の審査は省略されてきました。しかし、改正後は今まで「4号建築物」と言われていたものの殆どが「2号建築物」「3号建築物」となり審査の対象になる事になりました。■制度見直しのメリットと注意点
【メリット】
• 構造・防火性能の品質が一定以上に確保される
• 施工ミスや設計上の見落としを事前に防げる
• 地域ごとの実情に応じた柔軟な安全対策ができる
【注意点】
・確認申請書類の作成に時間がかかる。
・確認審査の手数料や、構造設計費などが追加で発生する可能性
・審査に時間がかかる分、着工時期が後ろ倒しになる場合も
▼用語説明
・4号建築物・・・二階以下で、延べ面積が500㎡以下、高さ13m、もしくは軒先9m以下の木造構造物(一般的な2階建て住宅)。また、木造、非木造、平屋200㎡以下もの
・建築確認・・・建築物を建てる時に、その計画が建築基準法などの法令に適しているか、工事着工前に審査する手続きのこと。
参考:関連する法令
• 建築基準法(eGov)
• 建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料 図解説明あり
• 建築物省エネ法(eGov)
②構造規制の合理化
■ 改正のポイント①壁倍率の上限が5倍→7倍に引き上げ
これまで壁の強さを表す「壁倍率」は最大5倍まででしたが、これが7倍に緩和され、耐力に優れた壁を柔軟に使えるようになりました。太陽光パネルや重い断熱材に対応しやすくなった点が評価されています。
②二級建築士でも中規模木造の設計が可能に
従来は、高さ13m超または軒高9m超の建築物は一級建築士でないと設計できないとされていました(建築士法施行規則)。今回の改正により、3階建てかつ高さ16m以下の木造住宅であれば、二級建築士でも設計・監理が可能となり、設計者の選択肢が広がりました。
③構造計算が必要な延床面積は、500超から300超に縮小
1. 近年、環境配慮や脱炭素化の流れから、中高層木造建築(CLT、ラーメン構造など)の普及が進んでいます。これにより、従来のような「小さいから安全」という想定が通用しなくなってきました。
2. 地震などによる安全性の確保 地震や台風による影響は無視できません。300㎡を超える建物での構造被害が確認されていることから、安全性向上の必要がありました。
3. 技術者による適切な設計が求められる時代に 今後は、木造であっても構造設計の専門的知見が不可欠になります。
▼用語説明
・500超・・・建物の延べ床面積が500㎡を超える事を意味しています。
・壁倍率・・・地震や台風などの水平力に対する強度を現わす数字で数字が大きい程耐震性能は高い
・構造計算・・・建物が地震や風などの外圧に耐えられるか、検証する計算 壁倍率の緩和や設計者の拡大は、より自由な間取りやコスト抑制を実現できる一方で、構造計算の義務強化により、設計者にはこれまで以上に高い構造知識や責任が求められるようになります。
参考:関連する法令
• 建築基準法(e-Gov法令検索)
• 建築士法施行規則(e-Gov)
• 建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料
③省エネ基準が義務化される
2025年4月、建築基準法および関係法令が改正され、新築住宅などのすべての建築物に省エネ基準の適合が義務化されました。これは、2050年のカーボンニュートラル実現を見据えたもので、住宅の「断熱性」や「エネルギー効率」を確保することが法律上のルールとなったのです。
■ 改正ポイント
従来、省エネ基準(建築物省エネ法に基づく)は、大規模な非住宅建築物(例:オフィスビルや商業施設など)には義務がありましたが、一般住宅(戸建てなど)は原則として努力義務にとどまっていました。
しかし、今回の改正により、すべての新築住宅・非住宅建築物に対して、省エネ性能(外皮断熱・一次エネルギー消費量など)を満たすことが法的義務となりました(建築物省エネ法第7条等)。
■ 対象と主な基準
対象となるのは新築されるすべての建築物(原則として300㎡以下も含む)です。
主な基準は以下の通り:
• 外皮性能(断熱)基準 → UA値(外皮平均熱貫流率)などで判断。地域区分ごとの断熱性能が求められます。
• 一次エネルギー消費量基準 → 冷暖房、給湯、換気、照明設備などの合計エネルギー使用量が基準以下であること。
・すべての新建築物は、省エネ適合性判定を受けなければならないので、施工スケジュールに影響が出る可能性があります。また、増改築の場合にはその部分も省エネ判定に適合させなければなりません。
▼用語説明
・外皮・・・建物の屋内外を隔てる窓などの開口部、屋根、壁、床などのこと
・一次エネルギー消費基準・・・建物の省エネ性のこと。
■ メリット
① 光熱費の削減 断熱・気密性の高い住宅は冷暖房効率が良く、光熱費を削減できる可能性があります。
② 快適な住環境 室温差が少なくなり、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を実現できます。
③ 資産価値の維持 省エネ基準を満たす住宅は、将来的に中古市場でも資産価値が下がりにくいと考えられています。
④ 補助金や減税の対象になりやすい 一定の省エネ性能を満たせば、各種の補助制度の対象になる可能性もあります。
■ デメリット・注意点
① 建築コストの上昇 高性能な断熱材や省エネ設備の導入により、建築費用が増加するケースもあります。
② 設計・施工の難易度アップ 省エネ基準への対応には、設計士や施工会社に専門知識と対応力が求められます。
③ 柔軟な設計の制約 開口部(窓)を大きくしたい、吹き抜けを設けたい、といった要望がある場合は、断熱性能との両立に工夫が必要になります。
参考:関連する法令
• 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)
• 建築基準法第20条(構造・設備の基準)改正の連携 建築確認申請において、適合判定が必要に。
• 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料
今回の省エネ基準義務化は、より快適で健康的な暮らしを支える住宅のスタンダード化を意味します。
多少のコスト増はあるものの、長期的には光熱費の節約や資産価値の維持など、十分なメリットも見込まれます。
④大規模木造建築物の防火規定の変更
■ 背景と目的
近年、環境負荷の低い建築資材として木材の需要が高まっており、学校、福祉施設、商業施設などでの大規模木造建築が注目されています。一方で、木造は「燃えやすい」というイメージから、防火上の厳しい制限を受けてきました。
今回の改正は、木造でも一定の防火性能を満たせば、大規模建築物にも利用できるようにすることで、木材利用の拡大と都市防災の両立を図るものです。
■ 改正ポイント 防火区画の緩和
延べ面積3,000㎡超の建築物などに必要だった**防火区画(耐火構造壁での分割)**について、木造でも一定の耐火性能(準耐火構造以上)を満たせば緩和可能となりました。 内装制限の合理化 従来は多くの木造建築で不燃材料による内装制限が必要でしたが、部位や用途に応じて木材の表しが可能になりました。
▼用語説明
・表し・・・露出させること。この場合は木材部分を露出させること。
■ 改正のメリット • デザインの自由度が向上
内装制限の緩和により、木材の質感を活かした空間づくりが可能となり、利用者にとっても快適性の向上が期待されます。
■ 改正のデメリット・注意点
• 防火設計の難易度が上がる
仕様規定が緩和された一方で、「性能評価」によって避難安全性を確認する必要があるため、設計には高度な知識と経験が必要となります。
• 施工の品質管理が重要に
木材の防火性能は、構造・接合部・被覆方法などに依存するため、不適切な施工は火災リスクを高めるおそれがあります。
• 確認申請の手続きが煩雑に
性能設計に基づく場合、審査機関への追加資料や検証手順が必要となり、設計期間が長くなる場合もあります。
今回の防火規定の見直しにより、木造建築の可能性は大きく広がります。 都市部でも木材を活用した大規模施設が実現しやすくなり、環境・経済・居住性のバランスを追求できるようになります。
参考:関連する法令
• 建築基準法施行令 第107条の2(防火区画)
• 国土交通省|2025年法改正資料「大規模木造建築の整備」
• 木造建築防火設計マニュアル(CLT協会ほか)
• 建築基準法・建築物省エネ法改正制度説明資料
⑤中高層木造建築の耐火性能基準の合理化
■改正ポイント
現行では、5階建てと、14階建ての建築物に対して同じ水準の防火基準が求められていましたが、
今回の改正により、5階以上、9階以下の建築物は最下層において90分以上の耐火性能で設計が可能になりました。
■木造中高層化のメリット
【環境面】
• 木材は再生可能資源であり、**CO₂の固定化(カーボンストック)**に貢献 • 建設時のCO₂排出量がRC造
・S造より少ないため、脱炭素社会の実現に近ずく事になる。
【空間性・快適性】
• 木材の断熱性能や調湿性により、快適で温かみのある居住空間が可能
• 商業施設や福祉施設などでも利用が広がりつつある
■注意点
・課題 中高層の木造建築物では、建築基準法に基づく厳格な防火
・耐火性能の確保が求められます。
• 構造部材ごとに求められる耐火時間(例:1時間、2時間)に適合した性能証明が必要です。
これは、柱・梁・床などが火災時に一定時間崩れないことを保証するためのものです。
• 木造であっても、CLT(直交集成板)や木質耐火部材を使う場合には、以下のいずれかの証明が必要です
国土交通大臣の認定(大臣認定)または、第三者機関による性能評価書 これらの書類により、使用する部材が所定の耐火性能を満たしていることを明確に示す必要があります。
• 耐火仕様の木材や特殊部材は高額になる場合があり、従来の木造よりもコストアップの懸念 • 設計・監理にも高い専門性が求められ、工期が延びる可能性もある
3. 行政手続きが煩雑になる可能性
• 防火地域内での木造建築には、確認審査の難易度が高くなる傾向
■制度の背景:公共建築物木材利用促進法との連携
この改正は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(木促法)」や、2050年カーボンニュートラル宣言の流れの一環として実施されています。
• 国は「木材利用促進本部」を設置し、公共施設だけでなく民間建築にも木造化を促進。
• 建築基準法の柔軟化により、都市部の建物にも木材を活用できる制度的土台の整備。
参考:関連する法令
国土交通省|建築基準法等の一部を改正する法律(令和6年4月施行)
⑥既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除
これまで、古い建物(既存不適格建築物)は現在の法律に合っていないため、増築や用途変更は原則として認められませんでした。しかし法律にすべて適合させるのは大変で費用もかかるため、多くの建物が空き家のまま放置される原因にもなっていました。
■改正ポイント
2025年4月に建築基準法では一部が改正され、一定の安全性を満たしていれば、用途変更や改修がしやすくなりました。 ■どんな活用例がある?
実際に想定される活用例は以下のようなものです。
• 築50年の木造住宅を耐震補強して小規模保育園に
• 使われていなかった旧旅館を改装し、地域の交流施設に
• 元倉庫をおしゃれなカフェやアートギャラリーに
■注意点
ただし、すべての古い建物が自由に使えるようになったわけではありません。
以下の点には注意が必要です。
1. 安全性の確保は絶対条件 耐震性が不十分だったり、避難経路がない場合は従来どおり利用が制限されます。
2. 専門家の調査が必要な場合も 用途変更が構造に関わる場合、建築士による調査や構造計算書が求められることもあります。
3. 一定の工事には建築確認申請が必要 増築や用途変更の内容によっては、役所や検査機関への申請が必要になります。
4. 地域ごとのルールに注意 自治体によっては、独自の安全基準や指導制度があるため、事前に確認しておきましょう。
適切な安全確認のもとで、地域のニーズに合わせた再活用の可能性が広がったことは、空き家問題の解決や持続可能なまちづくりにもつながります。 古い建物の活用を考えている方は、まず建築士や行政窓口に相談するのが第一歩です。新しい制度をうまく活かして、地域に価値ある空間を生み出していきましょう。
参考:関連する法令
• 【法令】建築基準法 第86条(既存不適格建築物の取り扱い)
• 【施行令】建築基準法施行令(構造・安全性の基準)
• 建築基準法・建築物省エネ法改正制度説明資料
まとめ

2025年4月の建築基準法改正は、これから家を建てる人や購入を考えている人にとって、知っておきたいポイントがたくさんあります。耐震性が上がったり、より暮らしやすいエコな家が実現したり、木造の中高層建物が建てやすくなったりと、自由で快適な住まいづくりがしやすくなる一方、コスト面、納期面では不安が残る点もあるでしょう。
法律の変更は難しく感じるかもしれませんが、信頼できる専門家と相談しながら最新の制度を味方にして、納得のいく住まい選びをしていきましょう。
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
理想の物件がきっと見つかる