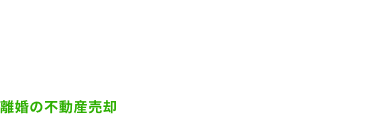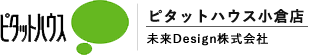不動産相続の流れとは?必要書類や2025年法改正・相続税の計算について徹底解説! | 宇治エリアの不動産購入、売却、賃貸のことなら未来Designへ
不動産相続の流れとは?必要書類や2025年法改正・相続税の計算について徹底解説!

不動産相続が発生すると、さまざまな手続きが必要となりますが、何をやるべきか曖昧だったり、どこに相談すればいいか分からなかったりと不安に思う方が多いかもしれません。
・不動産を相続する可能性がある
・不動産を相続した
そんな方は不動産の相続手続きについてよく理解しておくと良いでしょう。
今回は不動産を相続する流れや方法、必要書類について解説します。
【不動産を相続する流れ】

不動産の相続は、遺族にとって大切な手続きです。しかし、具体的な進め方がわからないと不安を感じることも多いでしょう。ここでは、不動産相続の基本的な流れをわかりやすく解説します。一歩ずつ確認しながら進めることで、スムーズな相続手続きが可能になります。
遺言書を確認する
不動産を相続する際、まず遺言書の有無を調べます。
遺言書がある場合、その内容が相続の進め方を大きく左右するからです。遺言者が遺言書の全文(遺産目録を除く)、遺言書の作成日付、遺言者氏名を自書し、押印する自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です。一方、遺言者が口述した遺言内容を公証人が記述する公正証書遺言であれば、すぐに手続きを進められます。遺言書が見つかった場合、勝手に開封せず、専門家に相談することが重要です。
相続人を確定させる
次に、相続人を特定します。法定相続人は、民法の規定に基づいて決定されます。例えば、配偶者は常に相続人となり、子どもや直系尊属(親など)も該当します。相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本を収集し、家族関係を確認します。この作業により、手続きをスムーズに進められます。
財産を特定して財産目録を作成する
相続する財産を特定するには、不動産や預貯金、負債などを洗い出します。不動産の場合は登記事項証明書を取得し、所在地や権利関係を確認する必要があります。
こうした情報を整理し、財産目録を作成することが求められます。財産目録は遺産分割協議の基礎資料となるため、正確に作成することが肝心です。
遺産分割協議を行う
相続人全員で話し合い、財産の分配方法を決めます。これを遺産分割協議と呼びます。協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し、全員の署名と押印を行います。
同意が得られない場合、家庭裁判所で調停や審判を行うことも検討されます。話し合いを円滑に進めるため、専門家の意見を取り入れるのも一つの方法です。
相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
遺産分割が決まった後、不動産の名義変更手続きを進めます。不動産の相続登記は法務局で行います。この手続きには、遺産分割協議書や被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などが必要です。
期限はありませんが、放置するとトラブルの原因になるため、早めの対応が求められます。
相続税の申告・納付
相続した財産の評価額が一定額を超える場合、相続税の申告が必要です。
申告期限は相続開始を知った翌日から10か月以内と定められています。期限を過ぎるとペナルティが課される可能性があるので注意が必要です。
不動産の評価は複雑な場合が多いため、税理士に相談することで安心して進められます。納税が必要な場合、分割払いの可否についても確認しておくと良いでしょう。
【相続登記に必要な9つの書類】

不動産の相続登記を行うためには、いくつかの書類が必要です。これらを適切に準備することで、手続きをスムーズに進めることができます。以下では、9種類の各書類の概要と取得方法について詳しく説明します。
登記申請書
登記申請書は、不動産の名義変更を申請するために必要な書類です。法務局の窓口やウェブサイトで入手できます。
申請書には、不動産の所在地や新しい所有者の情報を記載する必要があります。間違いがあると手続きが進まないため、慎重に作成しましょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、合意した内容を記した書類です。相続人全員の署名と押印が必要です。この書類は、相続人間のトラブルを防ぐためにも重要です。作成が難しい場合は専門家に依頼することをお勧めします。
戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本は、相続人を確定させるための証明書です。市区町村の役所で取得できます。出生から死亡までの戸籍が必要となるため、複数の役所から戸籍謄本を集める場合があります。取得には時間がかかることもあるので、早めに準備を始めましょう。
住民票
新しい所有者(相続人)の住民票が必要です。こちらも市区町村の役所で発行されます。住民票には住所や氏名が記載されており、不動産の新しい所有者情報を証明する役割を果たします。
印鑑証明書
印鑑証明書は、相続人が実印を使用していることを証明する書類です。市区町村の役所で取得可能です。遺産分割協議書の押印が実印であることを確認するために使用します。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、不動産の評価額を確認するための書類です。相続する不動産の所在地の市区町村から送付されるものを使用します。最新の通知書を用意してください。
相続関係説明図
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図式化したものです。法務局に提出することで、手続きが円滑になります。専門家に依頼して作成してもらうことも可能です。
収入印紙
相続登記の申請には、登録免許税として収入印紙を購入する必要があります。法務局や郵便局で購入可能です。税額は不動産の評価額に応じて変わるため、事前に確認しておきましょう。
登録免許税印紙納付台紙
収入印紙を貼付するための台紙です。法務局で配布されています。適切に記入し、必要な金額の収入印紙を貼付して提出します。
【重要!相続登記の申請義務化(令和6年4月開始)とは?】

相続登記の申請義務化は、令和6年4月から施行される重要な法改正です。
これまでは、相続が発生した後も相続登記をしなくても法的に罰則はありませんでしたが、今後は相続人に対して登記申請が義務付けられることになります。
この改正の目的は、空き家や不動産をめぐる問題を解消し、不動産の適切な管理と利用促進を図ることです。
相続登記の申請義務化により、相続が発生してから3ヶ月以内に登記手続きを行わない場合、罰則が課される可能性があります。
具体的には、相続登記を怠った場合、過料が科されることとなります。過料の金額は最大で10万円となっており、遅延や未登記によるトラブルの回避を促進することが狙いです。
相続登記は、不動産の所有者を明確にする重要な手続きです。申請義務化により、不動産の管理が明確化され、適切な所有権の移転が行われることが期待されています。
また、この義務化は、不動産取引における透明性を高め、未登記のままで放置されていた不動産の適正な利用を促進する役割も果たします。
今後、相続登記の申請を忘れないように、相続が発生した際には速やかに手続きを行うことが求められます。この改正によって、不動産の管理体制が一層整備され、社会全体の信頼性が向上することが期待されています。
【相続税の計算】

相続税とは、遺産を相続した際に発生する税金です。相続人が相続する財産の総額に応じて課税され、相続財産の価値が高いほど税額も増えます。相続税は、一定額を超える財産に対して課されるため、一定の基準を理解しておくことが重要です。
相続税は、相続財産の総額に基づいて計算されます。まずは相続財産をすべて計算し、次に基礎控除額を差し引き、残りの金額に税率を適用して税額を算出します。
基礎控除額の計算方法
相続税には基礎控除という仕組みがあり、一定額までは税金がかかりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。
相続税の税率
相続税は累進課税制度を採用しており、相続財産が多いほど税率が高くなります。税率は10%から最大55%まで、段階的に増加します。
実際の相続分と税額
相続税額は、法定相続分と実際の相続分によって異なる場合があります。実際に相続した財産に応じて、各相続人の税額が決まります。
控除や特例を活用する
相続税には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、さまざまな控除や特例が存在します。これらを上手に利用することで、税額を軽減できる可能性があります。
相続税の納付と注意点
計算された相続税額を納付する期限が定められており、期限を過ぎると延滞税が課されることもあるため納付期限を守ることが重要です。 「相続税が支払えない!」という方には下記の方法もあるので検討してみると良いでしょう。
相続税が払えない人必見!「不動産リースバック」の仕組みと3つのメリット
まとめ

不動産相続は、多くの手続きが伴い、専門知識を必要とするため、不安を感じることも少なくありません。
しかし、流れを理解し、必要書類をしっかり準備することで、スムーズに手続きを進めることができます。
まずは遺言書を確認し、相続人を確定させ、財産を特定することが第一歩です。その後、遺産分割協議を行い、名義変更の手続きを進め、相続税の申告を忘れずに行いましょう。
特に不動産に関しては、相続登記が義務化されることにより、遅延を避けることが求められます。相続税の計算方法や控除・特例を理解し、適切に活用することで、税負担を軽減できる場合もあります。
相続は大事な手続きになるので専門家のアドバイスを受けながら、円滑な進行を目指しましょう!
不動産相続をスムーズに進めるためのポイントや、相続した不動産を持て余している方は、こちらの記事で詳しく解説しているので合わせて参考にしてみてくださいね。
相続の前に知っておきたい!不動産相続をスムーズに行うための3つのポイント
相続した空き家を賢く売る3つのポイント「売却方法・税金・特例」について解説!
買う方が良いのか?借りる方が良いのか?
売る方が良いのか?貸した方が良いのか?
悩んでいる方はぜひ未来Designに相談をしてください。
理想の物件がきっと見つかる